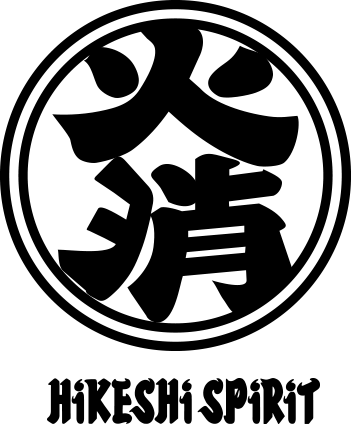Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts

Membership Program
会員プログラムについて
ご購入でポイントを獲得し、新商品に関する独占情報をお送りしております。
- ご購入でポイントを獲得:¥100で1ポイント。ポイントは¥1で、次回の購入にご使用できます。
- 新規会員には特別なキーチェーンをプレゼントし、登録時に最大500ポイントを獲得できます。
※キーチェーンは会員登録かつ、ご注文いただいた方に進呈 - 一定のポイントを累積すると、限定キーチェーンを受け取れます。
- ご登録時に300ポイント
- ニュースレター登録:200ポイント
- ¥100ごとに1ポイント獲得
- 特別な機会に追加ポイント
- 新商品の独占情報
- お誕生日に1000ポイント
注意:既存の会員による新規登録は、このキャンペーンの対象外となります。また、会員登録を繰り返すことで獲得したポイントは無効となります。発覚した場合、ご注文はキャンセルされます。
Exclusive Benefits
ヒケシスピリット会員特典や厳選アイテムの数々を、ご提供。


会員メリット 1
購入時にポイントが貯まる

会員メリット 2
ポイントアップイベント

会員メリット 3
限定の新作情報が届く
Invalid password
Enter